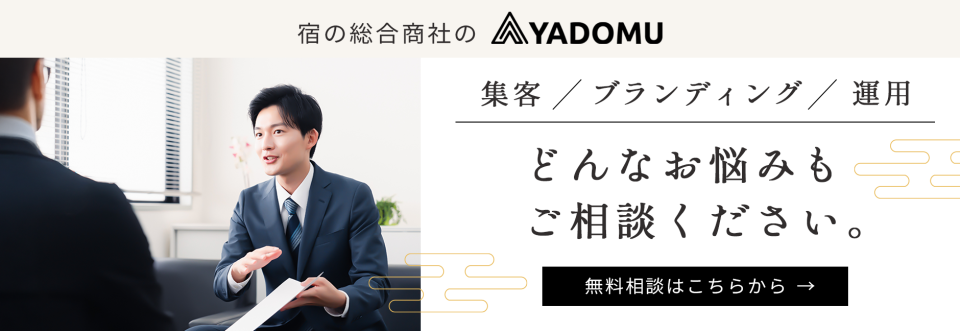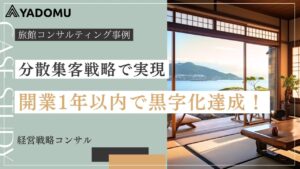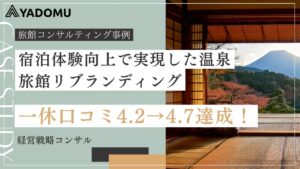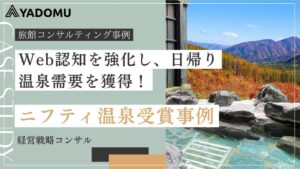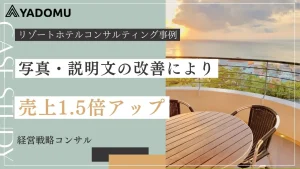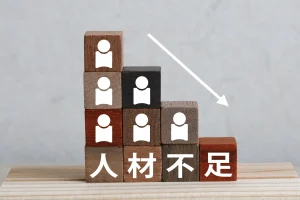- コラム
2025.07.31
ホテルの客室稼働率(OCC)の目安とは?稼働率を上げるコツも紹介
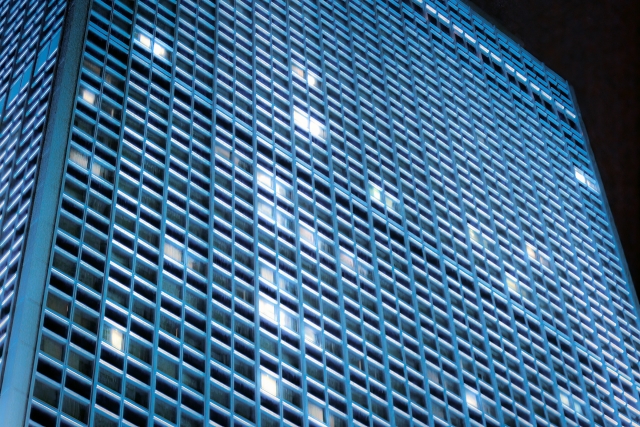
ホテル経営者の皆様にとって、客室稼働率は日々の運営状況を測る最も基本的で重要な指標です。しかし、その数字が持つ本当の意味や、業界内での立ち位置を正確に把握できているでしょうか。
稼働率の数字だけを追い求めても、必ずしも収益の最大化には繋がりません。重要なのは、稼働率と客室単価のバランスを取りながら、自社のホテルのポテンシャルを最大限に引き出す戦略を立てることです。
この記事では、ホテルの客室稼働率(OCC)の基本的な知識から、全国的な平均値、そして具体的な改善策までを網羅的に解説します。自社の現状を客観的に分析し、より収益性の高いホテル運営を実現するための一助となれば幸いです。
目次
Toggleホテルの客室稼働率(OCC)とは

ホテルの客室稼働率(OCC:Occupancy Rate)とは、ホテルが販売している全客室数のうち、実際に利用された客室数がどれくらいの割合を占めるかを示す指標です。この数値が高いほど、多くの客室が利用されていることを意味し、ホテル運営の効率性や人気度を測る基本的なバロメーターとなります。
客室稼動率は、以下の計算式で算出されます。
客室稼働率(OCC)(%) = 販売した客室数 ÷ 販売可能な総客室数 × 100
例えば、販売可能な客室が100室あるホテルで、ある日に70室が販売された場合、その日の客室稼働率は「70 ÷ 100 × 100 = 70%」となります。この指標を日次、月次、年次で追跡・分析することで、ホテルの運営状況を正確に把握し、経営戦略の立案に役立てることができます。
客室平均単価(ADR)との違い
客室平均単価(ADR:Average Daily Rate)は、販売した客室1室あたりの平均販売価格を示す指標です。売れた客室の平均的な値段がいくらだったかを表します。
計算式は以下の通りです。
客室平均単価(ADR)(円) = 客室売上合計 ÷ 販売した客室数
客室稼働率(OCC)が「どれだけ部屋が埋まったか」という量的な指標であるのに対し、ADRは「1室あたりいくらで売れたか」という価格的な指標です。稼働率が高くても、単価が低ければ売上は伸び悩みます。ホテルの収益性を評価する上では、この二つの指標を両輪で見ていく必要があります。
レヴパー(RevPAR)との違い
レヴパー(RevPAR:Revenue Per Available Room)は、販売可能な全客室1室あたりの売上がいくらだったかを示す指標で、ホテル経営の収益性を測る上で最も重要な指標の一つとされています。
計算式は以下の2通りです。
レヴパー(RevPAR)(円) = 客室売上合計 ÷ 販売可能な総客室数 レヴパー(RevPAR)(円) = 客室平均単価(ADR) × 客室稼働率(OCC)
客室稼働率(OCC)と客室平均単価(ADR)の両方の要素を掛け合わせて算出されるため、RevPARを見ることで、ホテルの総合的な収益力を評価できます。例えば、稼働率が90%でも単価が5,000円のホテル(RevPAR=4,500円)より、稼働率が70%でも単価が8,000円のホテル(RevPAR=5,600円)の方が、収益性は高いと判断できます。経営目標としては、このRevPARを最大化することが一つのゴールとなります。
採算ラインの算出方法

ホテルの経営を安定させるためには、自社の採算ライン、すなわち損益分岐点(BEP:Break-Even Point)を正確に把握しておくことが不可欠です。損益分岐点とは、売上と費用が等しくなり、利益がゼロになる点のことで、これを超えれば黒字、下回れば赤字となります。
採算ラインを算出する基本的な考え方は以下の通りです。
費用を「固定費」と「変動費」に分ける
- 固定費: 売上の増減に関わらず発生する一定の費用(人件費、地代家賃、減価償却費、保険料など)
- 変動費: 売上に比例して増減する費用(リネン代、客室アメニティ代、水道光熱費、OTA手数料など)
損益分岐点売上高を計算する
- 限界利益率 (%) = (売上高 – 変動費) ÷ 売上高 × 100
- 損益分岐点売上高 (円) = 固定費 ÷ 限界利益率
この損益分岐点売上高を達成するために、どれくらいの客室稼働率が必要になるかを逆算することで、「採算ラインとなる客室稼働率」を把握できます。この数値を下回ると赤字経営に陥るため、最低限達成すべき目標稼働率として常に意識しておく必要があります。
客室稼働率の目安

自社の客室稼働率が高いのか低いのかを判断するためには、業界全体の平均値を知ることが一つの参考になります。観光庁が毎月発表している「宿泊旅行統計調査」は、全国のホテルや旅館の稼働率を把握するための信頼性の高い公的データです。
コロナ禍で大きく落ち込んだ稼働率も、近年は回復傾向にあります。2023年の全国の宿泊施設における客室稼働率の平均は60.5%でした。これは、コロナ禍前の2019年の水準(63.9%)に迫る回復を見せています。ただし、この数値はあくまで全体の平均であり、施設のタイプや所在地によって稼働率の状況は大きく異なります。
業種別平均客室稼働率
宿泊施設と一言で言っても、その業態によってターゲット層や価格帯が異なるため、稼働率にも差が生じます。2023年の宿泊旅行統計調査によると、主な業態別の平均客室稼働率は以下のようになっています。
- 旅館: 40.3%
- リゾートホテル: 59.8%
- ビジネスホテル: 74.8%
- シティホテル: 73.6%
- 簡易宿所: 39.8%
ビジネスホテルやシティホテルは、出張などの安定したビジネス需要に支えられ、高い稼働率を維持していることがわかります。一方で、旅館やリゾートホテルは、季節性や観光需要の変動を受けやすく、稼働率が比較的低くなる傾向にあります。自社の業態の平均値と比較することで、より現実に即した立ち位置の分析が可能になります。
地域別平均客室稼働率
客室稼働率は、地域によっても大きく異なります。特に、インバウンド観光客に人気の高い大都市圏では、全国平均を上回る高い稼働率を示す傾向があります。2023年のデータを見ると、東京都が74.6%、大阪府が78.1%と、非常に高い水準で推移しています。
一方で、地方の観光地では、特定の観光シーズンに需要が集中し、年間を通じた平均稼働率は大都市圏に及ばないケースも多く見られます。自社のホテルが所在する都道府県や地域の平均稼働率をベンチマークとすることで、そのエリア内での競争力や、今後の伸びしろを測る上での重要な指標となります。
ホテル運営で客室稼働率を意識する重要性
客室稼働率は、単なる運営状況を示す数字以上の意味を持ちます。この指標を正しく理解し、意識することが、持続可能なホテル経営の基盤となります。
ホテルの収益に直結するため
客室稼働率は、ホテルの売上の根幹をなす客室部門の収益に直接的な影響を与えます。稼働率が1%上昇するだけでも、年間の売上は大きく変わってきます。稼働率を高めることは、売上の増加に直結する最も基本的なアクションです。
ただし、前述の通り、稼働率だけを追い求めて過度な安売りを行うと、ADR(客室平均単価)が低下し、結果としてRevPAR(収益性)が悪化する可能性もあります。稼働率と単価の最適なバランスを見つけることが、収益最大化の鍵となります。
運営効率の指標となるため
客室稼働率は、ホテルの運営がどれだけ効率的に行われているかを示す指標でもあります。高い稼働率を維持できているということは、集客戦略やマーケティング活動が成功している証拠です。
逆に、稼働率が低い状態が続く場合は、料金設定や販売チャネル、あるいはサービス内容そのものに何らかの問題がある可能性を示唆しています。稼働率のデータを分析することで、自社の強みや弱みを客観的に把握し、改善すべき点を特定するための重要な手がかりを得ることができます。
投資家からの信頼にも影響するため
ホテルを所有・運営する企業にとって、客室稼働率は外部からの評価を左右する重要な要素です。特に、不動産投資の対象としてホテルを見る投資家や金融機関は、RevPARと並んで客室稼働率を、そのホテルの収益安定性や将来性を判断するための重要なデータとして注視します。安定して高い稼働率を維持しているホテルは、事業としての信頼性が高いと評価され、融資や新たな投資を受けやすくなるなど、将来の事業拡大においても有利に働きます。
客室稼働率を上げるために取り入れたい施策
客室稼働率を向上させるためには、多角的なアプローチが必要です。ここでは、今日からでも検討できる具体的な施策をいくつか紹介します。
観光・宿泊需要のトレンドを取り入れる
宿泊者のニーズは時代と共に変化します。現在のトレンドを的確に捉え、自社のサービスに取り入れることが、新たな顧客層の獲得に繋がります。
例えば、近年ブームとなっている「サウナ」に注目し、質の高いサウナ施設を新設・リニューアルすることは、サウナ愛好家という新たなターゲット層に強くアピールできます。また、ワーケーション需要に応えるための高速Wi-Fiやワークスペースの整備、SDGsへの関心の高まりに応える環境配慮型アメニティの導入なども有効な施策です
設備を充実させ、リピーター獲得をねらう
一度訪れた顧客に「また来たい」と思わせ、リピーターになってもらうことは、安定した稼働率を維持する上で最も重要です。そのためには、顧客満足度を高めるための設備投資が欠かせません。
例えば、客室のベッドや寝具を高品質なものに入れ替えたり、バスアメニティにこだわったりするだけでも、顧客の滞在体験は大きく向上します。また、家族連れ向けにキッズスペースを設けたり、長期滞在者向けにキッチン付きの客室を用意したりと、ターゲット層に合わせた設備の充実が、リピーターの育成に直結します。
業務効率化をはかる
ホテルのフロント業務や予約管理は非常に煩雑であり、スタッフがこれらの業務に追われていると、本来注力すべき接客サービスの質が低下しかねません。PMS(宿泊管理システム)やサイトコントローラーといったITツールを導入し、予約管理や料金調整、顧客情報の一元管理などを自動化することで、業務は劇的に効率化します。これにより、スタッフはより心のこもったおもてなしに集中でき、顧客満足度の向上、ひいては稼働率の向上という好循環を生み出すことができます。
需要予測を行い、柔軟に価格設定する
過去の販売実績や周辺地域のイベント情報、季節性などのデータを基に、将来の宿泊需要を予測し、それに応じて客室料金を変動させる「レベニューマネジメント」は、収益最大化のための必須戦略です。
需要が高いと予測される日は料金を強気に設定し、逆に需要が低い閑散期には料金を下げてでも稼働を確保するといった、柔軟な価格設定が求められます。精度の高い需要予測を行うことで、機会損失を最小限に抑え、稼働率と単価の最適なバランスを実現できます。
OTAと公式サイトを併用する
OTA(オンライントラベルエージェント)は、新規顧客を獲得するための強力な集客チャネルです。一方で、販売手数料が発生するため、利益率は低下します。そこで重要になるのが、自社公式サイトからの直接予約を増やす取り組みです。
公式サイト限定の特典(レイトチェックアウト、ワンドリンクサービスなど)を用意したり、最低価格を保証する「ベストレート保証」を打ち出したりすることで、OTA経由の顧客を公式サイトでの予約へと誘導します。OTAでホテルの存在を知ってもらい、公式サイトで予約してもらうという流れを構築することが、利益率を確保しながら稼働率を上げるための理想的な形です。
パッケージプランを企画する
単なる宿泊だけでなく、食事やアクティビティ、地域の観光施設の入場券などを組み合わせた付加価値の高い「パッケージプラン」を企画することも、稼働率向上に有効です。例えば、「記念日向けディナー付きプラン」や「近隣テーマパークのチケット付きファミリープラン」、「地元の文化体験ができるプラン」など、ターゲット層の興味を引く魅力的なプランを用意することで、価格競争から一歩抜け出し、新たな需要を喚起することができます。
ホテルの稼働率を注視することはホテル経営の基本
ホテルの客室稼働率(OCC)は、経営の健全性を示す重要な指標ですが、その数字に一喜一憂するだけでは不十分です。重要なのは、ADR(客室平均単価)やRevPAR(収益性)といった他の指標と合わせて多角的に分析し、自社の立ち位置を正確に把握した上で、収益を最大化するための戦略を立て、実行していくことです。
今回ご紹介したように、稼働率を上げるためには、トレンドの導入や設備の充実といったハード面の強化から、業務効率化や柔軟な価格設定といったソフト面の工夫まで、多岐にわたる施策が考えられます。
特に、PMS(宿泊管理システム)やサイトコントローラーの導入による業務効率化は、スタッフの負担を軽減し、より質の高いサービス提供を可能にする、費用対効果の高い投資と言えます。日々の予約管理や料金調整に追われていると感じるなら、それは改善のチャンスです。
私たち宿夢は、旅館・ホテルのコンサルティング会社として、あらゆる課題解決のサポートをさせていただきます。
HP制作やSNSマーケティング、人材育成の支援まで多角的にお手伝いいたしますので、集客や採用、ブランディングなどにお困りでしたらお気軽にご相談ください。
コラム監修者

<略歴>
- 上智大学を卒業
- 大手企業向けERPシステムの開発・販売・サポートを行う企業に就職
- 経営資源に関するノウハウを培った後に、高級宿泊施設の予約サイトを運営する「株式会社一休」に転職。高級旅館・ホテルを累計300施設以上担当。
- 同時に、新サービス「一休.comふるさと納税」を2名で立ち上げ、初年度から事業の黒字化に成功。事業部長に就任し、事業をさらに急成長させた。
株式会社宿夢に参画してからは、1年で企業規模を倍にさせることに成功し、COOに就任。
<メディア掲載>
ホテル・旅館オーナー様向けナレッジ


お問合せ
無料相談承ります
WEB集客を図りたいがやり方がわからない
SNSの運用に人員と時間を割けない
アメニティを商品化したいが方法がわからない
こんなお悩みございましたら、まずは気軽にご相談ください。