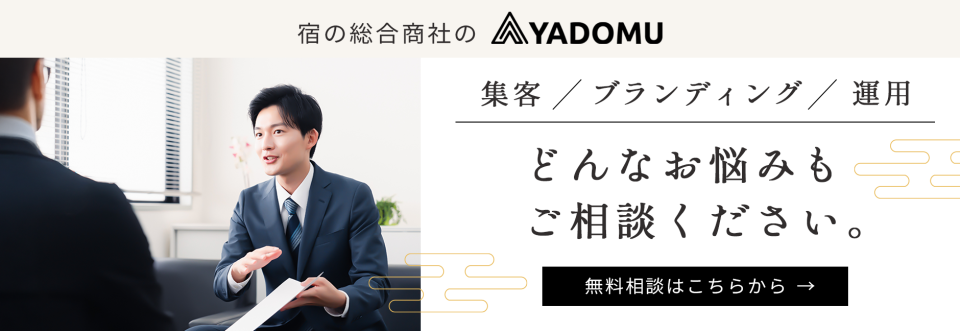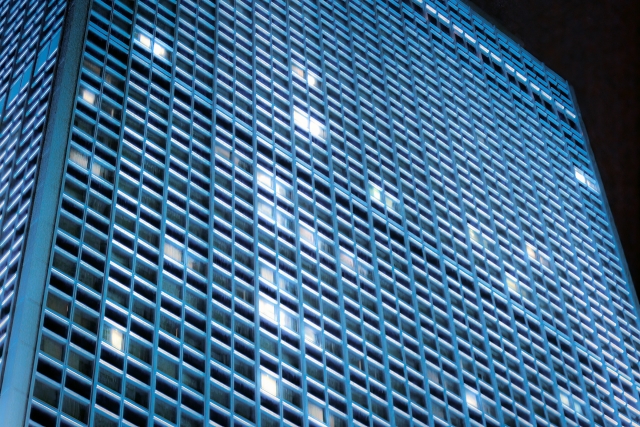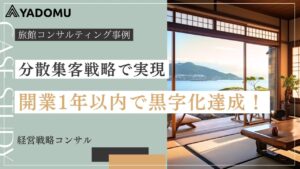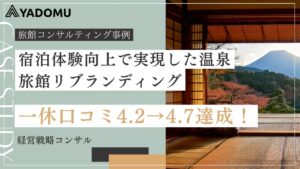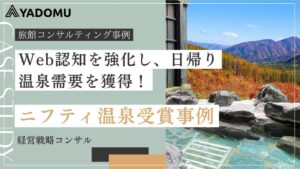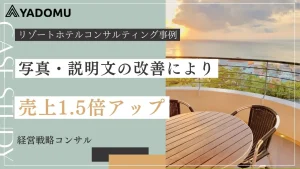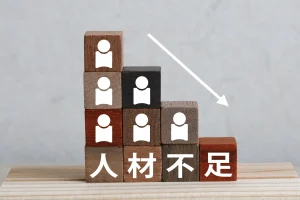- コラム
2025.07.31
ホテル経営の基礎知識を解説!必要な認可や経営形態なども紹介

本記事では、ホテル経営を成功に導くために不可欠な基礎知識を網羅的に解説します。経営形態の種類から、必要な許認可や資格、業界の動向、そして経営課題を乗り越えるための具体的なポイントまで、詳しく掘り下げていきます。
ぜひ、今後のホテル運営の指針としてお役立てください。
目次
Toggle変革を迎えるホテル経営の今

特に近年、ホテル業界は大きな変革の時を迎えています。
その背景から解説していきます。
国内旅行の回復
観光庁が発表した「宿泊旅行統計調査」によると、2023年の延べ宿泊者数は約5億9,351万人泊となり、コロナ禍以前の2019年と比較しても遜色のない水準まで回復しています。
特に日本人延べ宿泊者数は、2019年比で2.0%増となる約4億7,871万人泊に達し、国内旅行の力強い回復が示されました。
この背景には、長らく続いた行動制限からの解放感や、政府による観光支援策などが後押ししたことが考えられます。
インバウンド需要の増加
国内旅行の回復に加え、ホテル業界の活況を支えているのがインバウンド需要の急増です。日本政府観光局(JNTO)の発表では、2024年3月の訪日外客数は308万1,600人となり、単月で初めて300万人を突破しました。これは、2019年同月比で11.6%増という高い伸び率です。
歴史的な円安が外国人旅行者にとって大きな魅力となっているほか、航空路線の回復・増便も追い風となっています。インバウンド需要の取り込みは、客室単価の向上や新たな顧客層の開拓につながるため、今後のホテル経営において極めて重要な戦略となりま
ホテルの経営形態
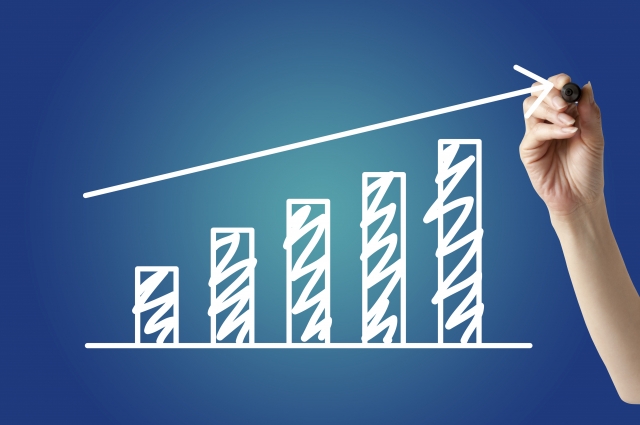
ホテル経営を始めるにあたり、まず理解しておくべきなのが経営形態です。それぞれの方式にメリット・デメリットがあり、自己資金や運営ノウハウの有無、目指すホテル像によって最適な選択肢は異なります。
ここでは、代表的な4つの経営形態について解説します。
所有直営方式
所有直営方式とは、土地や建物の所有者(オーナー)が、ホテルの経営・運営も自ら直接行う形態です。ホテルの運営に関する全ての意思決定を自社で行えるため、独自のコンセプトやサービスを追求しやすく、自由度の高い経営が可能です。
運営が成功すれば、得られた利益のすべてが自社の収益となる点も大きな魅力と言えるでしょう。
一方で、ホテルの建設や取得にかかる多額の初期投資が必要になるほか、運営に関するすべての責任を負うことになります。人材の採用・育成から、集客マーケティング、日々のオペレーションまで、幅広い専門知識とノウハウが求められるため、経営の難易度は高い方式です。経営が軌道に乗らなかった場合のリスクも全て自社で抱えることになります。
MC方式(管理運営受託方式)
MC方式(Management Contract)は、土地・建物の所有者(オーナー)が、ホテルの運営業務を専門の運営会社(オペレーター)に委託する形態です。ホテル運営のプロに経営を任せるため、オーナーは運営ノウハウがなくてもホテル事業に参入できます。有名ホテルブランドの運営会社に委託すれば、そのブランド力を活用した高い集客効果も期待できるでしょう。
オーナーは運営会社に対して、売上や利益に応じた運営委託手数料を支払います。所有直営方式に比べて運営に関するリスクは軽減されますが、経営の自由度は低くなります。
運営方針は基本的に運営会社が決定するため、オーナーの意向が反映されにくい側面がある点には注意が必要です。また、運営会社の選定が、経営の成否を大きく左右する重要なポイントとなります。
リース方式
リース方式は、土地・建物の所有者(オーナー)が、ホテル運営会社に施設を一括で賃貸し、運営会社が経営を行う形態です。オーナーは運営会社から毎月固定の賃料を受け取ります。ホテルの業績に関わらず安定した収入が見込めるため、リスクを抑えて不動産を有効活用したい場合に適した方式です。
運営はすべて運営会社が行うため、オーナーはホテル経営に直接関与する必要がありません。ただし、得られる収益は賃料収入に限られ、ホテルが大きな利益を上げたとしても、その恩恵を直接受けることはできません。契約内容によっては、長期間にわたる賃料の固定化や、中途解約が難しいといった制約が生じる可能性もあります。
フランチャイズ方式
フランチャイズ方式は、オーナーがフランチャイズ本部に加盟し、そのブランド名やロゴ、運営ノウハウなどを利用してホテルを経営する形態です。加盟金やロイヤリティを支払うことで、確立されたブランドの知名度や集客力を活用できるため、特にホテル経営の経験がない場合に有効な選択肢となります。
本部から運営マニュアルや研修プログラムが提供されるため、比較的スムーズに事業を開始できる点が大きなメリットです。しかし、経営の自由度は低く、本部が定めた運営ルールやサービス基準を遵守する必要があります。独自のサービス展開や、内装の変更などが制限される場合も少なくありません。また、ブランドイメージの毀損といった、自社ではコントロールできないリスクの影響を受ける可能性もあります。
ホテルの収益の中心となる部門

ホテルの収益構造は、主に「宿泊部門」「飲食部門」「宴会・イベント部門」の3つの柱で成り立っています。これらの部門がそれぞれ連携し、収益を最大化することが安定したホテル経営の鍵となります。
宿泊部門
宿泊部門は、客室の販売によって収益を上げる、ホテルビジネスの根幹をなす部門です。収益の基本は「客室単価 × 客室稼働率」で計算されます。この部門の利益率は他の部門に比べて高い傾向にあり、ホテル全体の収益性を大きく左右します。
そのため、いかに客室稼働率を高め、適正な客室単価を維持・向上させるかが経営上の重要な課題となります。季節や曜日、周辺イベントの有無などに応じて価格を変動させる「レベニューマネジメント」の手法を取り入れ、収益の最大化を図ることが求められます。フロント業務の効率化や、快適な客室環境の提供といった、顧客満足度を高める取り組みも不可欠です。
飲食部門
飲食部門は、ホテル内に併設されたレストランやバー、ラウンジ、ルームサービスなどで飲食物を提供し、収益を上げる部門です。宿泊客だけでなく、外来の顧客も利用するため、ホテルの魅力を外部にアピールする「顔」としての役割も担います。
飲食部門の充実は、宿泊客の満足度向上に直結し、ホテルのブランドイメージを高める効果も期待できます。朝食、ランチ、ディナーといった時間帯ごとのニーズに応えるメニュー開発や、地域の特産品を活かした独自性の高い料理の提供が、他ホテルとの差別化につながります。ただし、食材の仕入れコストや人件費がかさむため、宿泊部門に比べて利益率は低くなる傾向があります。
宴会・イベント部門
宴会・イベント部門は、結婚披露宴や企業の会議、セミナー、展示会、パーティーなどの会場として施設を提供し、収益を上げる部門です。一度に多くの集客が見込めるため、売上の規模が大きくなる特徴があります。
この部門は、会場のレンタル料だけでなく、それに付随する飲食サービスの提供や音響・照明設備の利用料など、多様な収益源を持っています。平日の稼働率を高めるために法人向けの研修プランを充実させたり、週末には地域住民向けのイベントを企画したりするなど、ターゲットに応じた柔軟な営業戦略が求められます。宴会やイベントの成功は、ホテルの知名度向上や将来の顧客獲得にもつながる重要な役割を果たします。
ホテル経営に必要な許認可
ホテルを経営するためには、関連する法律に基づき、行政からいくつかの許認可を得る必要があります。これらの許認可なく営業を行うことは法律で固く禁じられています。計画段階でどの許認可が必要になるかを正確に把握し、準備を進めることが重要です。
旅館業法に基づく営業許可
ホテルや旅館、簡易宿所などを開業する上で、最も基本となるのが「旅館業法」に基づく営業許可です。この許可を得るためには、施設の構造設備が定められた基準(客室の数や面積、換気・採光、衛生設備など)を満たしている必要があります。
申請は、ホテルの所在地を管轄する保健所に対して行います。申請書類には、営業許可申請書のほか、建物の図面や消防法令適合通知書、水質検査成績書の写しなど、多くの添付書類が求められます。手続きには時間を要するため、開業予定日から逆算して、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが肝心です。
飲食店営業許可(食品営業許可)
ホテル内のレストランやカフェ、バーなどで調理した飲食物を提供する場合は、「食品衛生法」に基づく飲食店営業許可が別途必要になります。この許可も、管轄の保健所に申請します。
許可を得るためには、厨房設備が衛生基準を満たしていることや、食品衛生責任者を設置していることなどが要件となります。厨房のシンクの数や給湯設備、冷蔵庫の温度計設置など、細かな規定が定められています。ルームサービスで食事を提供する場合や、朝食ビュッフェを行う場合もこの許可の対象となるため、飲食物を提供する全てのケースで取得が必須と捉えておきましょう。
酒類販売業免許
レストランやバー、客室のミニバーなどで、栓を開けずに瓶や缶のままお酒を提供(販売)する場合には、「酒税法」に基づき税務署から「酒類販売業免許」を取得する必要があります。具体的には、お土産としてボトルワインを販売したり、客室のミニバーで缶ビールを販売したりするケースが該当します。
一方で、レストランやバーでグラスに注いで提供するなど、栓を開けて飲用させる場合は飲食店営業許可の範囲内となり、酒類販売業免許は不要です。提供形態によって必要な免許が異なるため、どのような形でお酒を扱うのかを明確にし、税務署に確認することが大切です。
公衆浴場許可
設置する浴場が、宿泊者だけでなく日帰り入浴などで宿泊しない人も利用できる「大浴場」である場合、「公衆浴場法」に基づく許可が必要になることがあります。この法律は、公衆の衛生を確保することを目的としており、浴槽の管理方法や水質基準などが厳しく定められています。
一方で、宿泊者のみが利用する大浴場であれば、基本的に旅館業法の範囲内となり、公衆浴場許可は不要です。日帰り温浴プランなどを設けて集客の幅を広げたい場合は、この許可の取得を検討する必要があります。申請先は同様に管轄の保健所となります。
ホテル経営に必要な資格
ホテルを安全かつ合法的に運営するためには、特定の業務を行うための国家資格を持つ従業員の配置が法律で義務付けられています。これらの資格者を確保することは、コンプライアンス遵守だけでなく、お客様と従業員の安全を守る上でも極めて重要です。
消防設備士
消防設備士は、ホテルに設置されているスプリンクラーや自動火災報知設備、消火器といった消防用設備の点検・整備を行うために必要な国家資格です。消防法により、ホテルなどの特定防火対象物では、有資格者による定期的な点検と、その結果の消防署への報告が義務付けられています。
点検・整備を外部の専門業者に委託することも可能ですが、従業員が資格を取得していれば、日常的な管理や軽微な不具合への対応が迅速に行えるほか、コスト削減にもつながります。お客様の安全に直結する重要な役割を担う資格です。
防火管理者
防火管理者は、ホテル全体の防火管理体制を統括する責任者です。消防法に基づき、ホテルの収容人員が30人以上の場合には、防火管理者の選任が義務付けられています。
主な職務は、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施、消防用設備の点検・整備の監督、火気の使用や取り扱いの監督など多岐にわたります。火災の発生を未然に防ぎ、万が一発生した際に被害を最小限に抑えるための中心的な役割を担います。資格は、日本防火・防災協会などが実施する講習を受講することで取得できます。
食品衛生責任者
レストランや宴会場など、飲食物を提供する施設には、食品衛生法に基づき「食品衛生責任者」を各施設に1名以上置くことが義務付けられています。食品衛生責任者は、施設の衛生管理を担い、食中毒などの食品事故を防止する重要な役割を持ちます。
調理師や栄養士などの資格を持っている者は、講習を受けずとも食品衛生責任者になることができます。それ以外の人が資格を取得する場合は、都道府県知事などが指定した養成講習会を受講する必要があります。従業員の健康管理や、食材の適切な取り扱い、調理器具の洗浄・消毒などを徹底し、食の安全を守ります。
危険物取扱者(乙種4類)
ホテル内でボイラーや自家発電設備の燃料として、ガソリンや灯油、重油といった引火性液体(危険物第4類)を、指定数量以上貯蔵または取り扱う場合に必要となる国家資格です。資格を持った危険物取扱者が、自ら取り扱うか、あるいは取り扱いに立ち会うことが消防法で義務付けられています。
特に、大規模なホテルで暖房や給湯のために重油などを使用するボイラーを設置している場合に、この資格者が必要となります。燃料の安全な管理と運用を行い、火災や漏洩といった事故を未然に防ぐための専門知識が求められます。
ボイラー技師(二級)
ボイラー技士は、ホテル内の給湯や暖房、厨房などで使用されるボイラーを安全に取り扱うために必要な国家資格です。労働安全衛生法に基づき、伝熱面積の合計が25㎡以上など、一定規模以上のボイラーを取り扱う事業場では、ボイラー技士の免許を持つ者の中からボイラー取扱作業主任者を選任することが義務付けられています。
ボイラーは、正しく管理しないと破裂などの大事故につながる危険性があります。ボイラー技士は、日常の運転操作や点検、異常時の対応などを行い、設備の安全な稼働を維持する責任を負います。資格は、実務経験を積んだ上で、安全衛生技術試験協会が実施する免許試験に合格することで取得できます。
ホテル経営に必要な初期費用
ホテル経営を始めるには、多額の初期費用が必要となります。特に土地の取得や建物の建設から始める場合、その費用は数十億円規模に上ることも珍しくありません。ここでは、主な初期費用の内訳について解説します。
まず最も大きな割合を占めるのが「物件取得費」です。これには土地代と建物代が含まれます。立地や規模によって費用は大きく変動し、都市部の一等地であれば土地代だけで莫大な金額になります。中古物件を改装する「リノベーション」という選択肢もありますが、それでも大規模な改修が必要となれば億単位の費用がかかるでしょう。
次に必要なのが「内装・設備工事費」です。客室のベッドや家具、ユニットバス、壁紙、照明といった内装費用に加え、業務用厨房設備、空調設備、エレベーター、受変電設備など、ホテル運営に不可欠な各種設備の導入費用がかかります。快適性と機能性を両立させるための投資は、顧客満足度に直結するため非常に重要です。
さらに、「備品購入費」も考慮しなければなりません。客室のリネン類(シーツ、タオル)、アメニティグッズ、食器、調理器具、従業員の制服など、日々の運営に必要な消耗品や備品を揃える費用です。
これらに加え、Webサイトの制作や予約システムの導入にかかる「ITシステム関連費」、開業前の広告宣伝費、そして許認可申請にかかる費用や、当面の運転資金も準備しておく必要があります。自己資金だけで全てを賄うのは困難なケースが多いため、多くの場合は金融機関からの融資を活用することになります。その際には、説得力のある事業計画書の作成が不可欠です。
ホテル業界の現状と今後の動向
現在のホテル業界は、コロナ禍という未曾有の危機を乗り越え、回復から成長のフェーズへと移行しています。前述の通り、国内旅行需要の回復と、歴史的な円安を背景としたインバウンド需要の爆発的な増加が、業界全体に強い追い風となっています。
特にインバウンドにおいては、これまで人気だった東京・大阪・京都といったゴールデンルート以外の地方都市にも関心が広がり始めており、地域経済の活性化にも大きく貢献しています。政府も2030年に訪日外国人旅行者数6,000万人という高い目標を掲げており、今後も市場の拡大が期待されます。
一方で、業界は大きな変化の波に直面しています。旅行者のニーズは多様化・パーソナライズ化しており、単に宿泊するだけの場所から、その土地ならではの「体験」を求める傾向が強まっています。ワーケーションやウェルネスツーリズムといった新しい旅のスタイルも定着しつつあり、これらに対応できないホテルは淘汰される可能性があります。
また、サステナビリティ(持続可能性)への関心も高まっており、環境に配慮したホテル運営(省エネ、食品ロス削減、アメニティの見直しなど)は、企業の社会的責任としてだけでなく、新たな顧客層にアピールする上でも重要な要素となっています。今後は、デジタル技術を活用した業務効率化や顧客体験の向上(DX)と、環境や社会に配慮した経営(SX)の両立が、持続的な成長のための鍵となるでしょう。
ホテル経営でよくある課題
ホテル業界が活況を呈する一方で、多くの経営者は共通の課題に直面しています。これらの課題にいかに向き合い、対策を講じるかが、経営の安定化と成長の分かれ目となります。
人手不足
最も深刻な課題の一つが、全セクションにわたる人手不足です。コロナ禍で多くの人材が他業種へ流出した影響が大きく、需要が急回復した現在、フロント、客室清掃、レストランスタッフなど、あらゆる部門で人材の確保が困難になっています。
人手不足は、サービスの質の低下を招き、顧客満足度の悪化に直結します。また、既存の従業員に過度な負担がかかることで、離職率がさらに高まるという悪循環に陥りかねません。採用競争が激化する中で、いかに魅力的な労働環境を提供し、人材を確保・定着させるかが喫緊の課題です。
収益性の維持・アップが難しい
需要の回復に伴い客室単価は上昇傾向にありますが、一方でエネルギー価格の高騰や原材料費の上昇、人件費の増加といったコストプッシュ圧力も強まっています。これらのコスト増を宿泊料金に適切に転嫁できなければ、利益が圧迫され、収益性は悪化してしまいます。
また、オンライン旅行会社(OTA)への手数料支払いや、乱立する競合ホテルとの価格競争も、収益性を圧迫する要因です。単に価格を上げるだけでなく、付加価値の高いサービスを提供したり、飲食部門や宴会部門など宿泊以外の収益源を強化したりするなど、多角的な収益改善策が求められます。
社会情勢や景気の影響が大きい
ホテル業界は、景気の動向、自然災害、感染症のパンデミック、国際情勢といった外部環境の変化に極めて敏感な産業です。景気が後退すれば、企業の出張や個人の旅行は真っ先に抑制され、需要が大きく落ち込みます。
コロナ禍での経験は、予測不可能な事態が事業の根幹を揺るがしかねないという教訓を、業界全体に残しました。特定の顧客層(例えば、インバウンドやビジネス客)に依存しすぎると、有事の際に大きな打撃を受けます。リスクを分散させるために、ビジネスとレジャー、国内と海外など、バランスの取れた顧客ポートフォリオを構築することが重要です。
自動化できていない業務が多い
ホテル業界は、伝統的に「人」によるおもてなしを重視してきたため、他の産業に比べてデジタル化や自動化が遅れている側面があります。フロントでのチェックイン・アウト手続き、電話による予約・問い合わせ対応、客室清掃の管理など、いまだに手作業や紙ベースで行われている業務が少なくありません。
これらの非効率な業務は、人手不足をさらに深刻化させる原因となっています。また、従業員が単純作業に時間を取られることで、本来注力すべき質の高い顧客サービスの提供がおろそかになる可能性もあります。業務プロセスの見直しと、適切なITツールの導入による自動化が急務と言えるでしょう。
施設の老朽化
建設から数十年が経過したホテルでは、建物の老朽化が深刻な課題となります。外壁の劣化や配管の腐食、空調設備の機能低下などは、修繕に多額の費用がかかるだけでなく、放置すれば顧客満足度の低下や安全性の問題にもつながります。
特に、客室の古さや水回りの不具合は、宿泊客の評価に直接影響します。現代の旅行者のニーズに合った内装や設備へのリニューアルは、競争力を維持するために不可欠な投資です。しかし、大規模な改修には多額の資金と、場合によっては一時的な休業が必要となるため、計画的な資金繰りと長期的な視点での投資判断が求められます。
ホテルの経営課題を改善するポイント
前述したような課題を乗り越え、ホテル経営を成功に導くためには、現状を的確に分析し、戦略的な改善策を実行していく必要があります。ここでは、経営改善のための3つの重要なポイントを解説します。
労働環境を見直して離職を防ぐ
深刻な人手不足に対応するためには、新規採用に力を入れると同時に、既存の従業員の離職を防ぐ「リテンションマネジメント」が極めて重要です。従業員が働きがいを感じ、長く勤めたいと思える環境を整備することが不可欠です。
具体的には、適切な給与水準の確保や、能力・成果に基づいた公正な評価制度の導入が挙げられます。また、長時間労働の是正、休日休暇の取得促進、多様な働き方(時短勤務など)の導入といった、ワークライフバランスへの配慮も欠かせません。従業員一人ひとりのキャリアプランを支援する研修制度を充実させることも、モチベーション向上と定着率アップにつながります。
宿泊単価や客室稼働率を上げる施策を考える
収益性を向上させるためには、事業の根幹である「宿泊単価(ADR)」と「客室稼働率(OCC)」の双方を高める施策が必要です。稼働率を高めるためには、公式ウェブサイトからの直接予約を増やすためのSEO対策やWeb広告、リピーター向けのメルマガ配信などが有効です。
宿泊単価を上げるには、単なる値上げではなく、価格に見合うだけの付加価値を提供することが重要になります。例えば、地元の食材をふんだんに使った魅力的な朝食プランの提供、記念日向けの特別パッケージの造成、地域文化を体験できるアクティビティとの連携などが考えられます。レベニューマネジメントを高度化し、需要に応じて価格を最適化する取り組みも収益最大化に貢献します。
業務のDXを推進する
人手不足の解消と生産性向上の切り札となるのが、業務のデジタルトランスフォーメーション(DX)です。PMS(宿泊管理システム)やサイトコントローラーを導入し、予約管理や料金調整を自動化することは今や必須と言えます。
さらに、スマートロックを導入してチェックイン・アウトを無人化・省力化したり、清掃管理システムで客室の状況をリアルタイムに共有したりすることで、業務は大幅に効率化されます。また、CRM(顧客関係管理)ツールを活用して顧客データを分析し、個々の顧客に合わせたパーソナライズされたサービスを提供することも、顧客満足度とリピート率の向上につながります。DXはコスト削減だけでなく、新たな顧客体験を創出するための重要な投資です。
ホテル経営は追い風もあるが課題も多くやりがいのある事業
本記事では、ホテル経営の基礎となる経営形態や必要な許認可、収益構造から、現代のホテル業界が直面する課題と、それを乗り越えるための改善ポイントまでを詳しく解説しました。
ホテル経営は、国内旅行やインバウンド需要の回復という追い風がある一方で、人手不足、コスト高騰、施設の老朽化など、多くの複雑な課題が絡み合う、難易度の高い事業です。これらの課題に立ち向かい、持続的な成長を遂げるためには、自社の強みと弱みを客観的に分析し、データに基づいた戦略的な意思決定を行っていく必要があります。
しかし、日々の運営に追われる中で、中長期的な視点での経営改善や、専門知識を要するDXの推進、効果的なマーケティング戦略の立案・実行まで、すべてを自社だけで行うのは容易ではありません。
もし、収益改善や業務効率化、人材育成など、ホテル経営に関するお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たち宿夢にご相談ください。宿夢は、旅館・ホテルに特化したコンサルティングサービスを提供しており、数多くの宿泊施設の経営改善をサポートしてきた実績がございます。現場目線に立った実践的なノウハウで、貴館が抱える課題を解決し、未来への成長を力強く後押しします。
コラム監修者

<略歴>
- 上智大学を卒業
- 大手企業向けERPシステムの開発・販売・サポートを行う企業に就職
- 経営資源に関するノウハウを培った後に、高級宿泊施設の予約サイトを運営する「株式会社一休」に転職。高級旅館・ホテルを累計300施設以上担当。
- 同時に、新サービス「一休.comふるさと納税」を2名で立ち上げ、初年度から事業の黒字化に成功。事業部長に就任し、事業をさらに急成長させた。
株式会社宿夢に参画してからは、1年で企業規模を倍にさせることに成功し、COOに就任。
<メディア掲載>
ホテル・旅館オーナー様向けナレッジ


お問合せ
無料相談承ります
WEB集客を図りたいがやり方がわからない
SNSの運用に人員と時間を割けない
アメニティを商品化したいが方法がわからない
こんなお悩みございましたら、まずは気軽にご相談ください。